SDGs(持続可能な開発目標)とは
SDGsが掲げる17のゴール(目標)について

SDGsとは、(Sustainable Development Goals)の略で、「持続可能な開発目標」と訳します。「世界中にある差別や貧困、飢餓、環境問題などの課題を、世界のみんなで2030年までに解決していく」という計画・目標のことです。2030年を達成年限とし、17の目標と169のターゲットから構成されています。
SDGsは世界全体で取り組むべき課題ですが、その中には身近に感じられないものもあるかもしれません。しかし、大切なのは、私たち一人ひとりが2030年以降の未来を見据え、日々の暮らしの中で無理なくできることから行動を始めることです。
例えば、身の回りのものを大切にして長く使うことや、ごみを出す際にリサイクルを意識して分別することなども、SDGs達成に向けた大事な一歩です。こうした小さな行動が、未来に繋がる大きな変化を生み出します。
ゴール1 貧困をなくそう

「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」
「貧困をなくそう」—私達ができる身近な取組
【フードドライブ参加】
余った食料を寄付して、困っている人を助ける。
【物品寄付】
不要な衣類や日用品を寄付し、必要な家庭を支援。
【地域で支え合い】
困っている人に手を差し伸べ、助け合いの精神を広げる。
【教育支援】
学用品の寄付や勉強のサポートで、子どもたちの未来を支える。
小さな取組が大きな変化を生みます。みんなで一緒に貧困削減に貢献しましょう!
「貧困をなくそう」—自治体行政の関係
自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。 各自治体において、すべての町民が必要最低限の暮らしを確保することができるよう、きめ細やかな支援策が求められています。
ゴール2 飢餓をゼロに

「飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」
「飢餓をゼロに」—私達ができる身近な取組
【フードドライブへの寄付】
家庭で余った食品をフードバンクに寄付し、飢餓に苦しむ人々を支援。
【食料ロスの削減】
食品を無駄にせず、適切に保存・消費することで、食料資源を有効活用。
身近な行動が飢餓を減らすための大きな力になります。みんなで「飢餓ゼロ」を目指していきましょう!
「飢餓をゼロに」—自治体行政の関係
自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して、農業や畜産などの食料生産の支援を行うことが可能です。そのためにも、適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。
ゴール3 すべての人に健康と福祉を

「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」
「すべての人に健康と福祉を」—私達ができる身近な取組
【健康づくりの参加】
ウォーキングイベントや地域のスポーツ活動に参加し、健康な体づくりに取組む。
【地域の高齢者支援】
高齢者に声をかけ、買い物や日常的なサポートを行うことで、孤立を防ぎ福祉を広げる。
【ボランティア活動の参加】
福祉施設や地域イベントでボランティアとして参加し、助けが必要な人々を支援。
【食生活の改善】
地元の食材を使った健康的な食事を心がけ、栄養バランスの良い生活を促進。
町民一人ひとりが小さな支援を積み重ねることで、誰もが健康で幸福な生活を送れる社会を作りましょう!
「すべての人に健康と福祉を」—自治体行政の関係
住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態を維持・改善に必要であるという研究も報告されています。
ゴール4 質の高い教育をみんなに
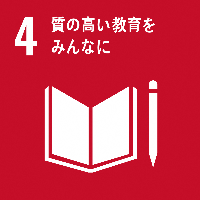
「すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」
「質の高い教育をみんなに」—私達ができる身近な取組
【学習支援活動】
地域の子どもたちに勉強を教えたり、宿題を手伝うことで、学びのサポートを行う。
【教材や学用品の寄付】
使わなくなった学習用品や本を寄付して、学ぶ機会を増やす。
身近な取組が、教育の質を高める手助けになります。みんなで学び合い、支え合う社会を作りましょう!
「質の高い教育をみんなに」—自治体行政の関係
教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては、自治体が果たすべき役割は非常に大きいと言えます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行政の取組は重要です。
「質の高い教育をみんなに」-高鍋町中学生短期留学派遣事業【事業実施課:教育総務課】

約3週間のオーストラリア短期留学を終えた高鍋東中学校2名と高鍋西中学校2名の生徒たち
本事業は、次世代を担う中学生を海外へ留学させ、単なる「語学力」や「異文化理解力」の習得にとどまらず、グローバル社会で必要となる「挑戦する力」「コミュニケーション力」「積極性」といった「自ら未来を切り拓く力」を身に付けさせることを目的に実施しています。
令和5年度より、オーストラリアへ中学生を毎年派遣しています。本年度も選抜された4名の生徒を派遣し、国際的な視野を広げる貴重な機会を提供しました。
本事業は、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」の達成に貢献しています。
ゴール5 ジェンダー平等を実現しよう

「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」
「ジェンダー平等を実現しよう」—私達ができる身近な取組
【平等な機会の提供】
性別に関係なく、仕事や活動で平等な機会を提供し、差別をなくす。
【家庭内での役割分担】
家事や育児を共同で行い、性別に関係なく支え合う家庭を作る。
【ジェンダーに配慮した言動】
性別に基づく偏見やステレオタイプを避け、誰もが安心できる環境を作る。
町民一人ひとりが小さな意識を持ち、実践することで、より平等な社会を築いていきましょう!
「ジェンダー平等を実現しよう」—自治体行政の関係
自治体による女性や子ども等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自治体行政や社会システムにジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審議会委員等における女性の割合を増やすのも重要な取組と言えます。
ゴール 6 安全な水とトイレを世界中に

「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」
「安全な水とトイレを世界中に」—私達ができる身近な取組
【水の節約】
家庭での水の使い方に気を付け、無駄な水の使用を減らすことで、限りある資源を守る。
【地域の清掃活動】
公園や河川等の清掃に参加し、衛生的な環境を保つことで、安全な水源を守る。
【トイレの衛生管理】
家庭や地域でトイレを清潔に保ち、衛生環境の向上を意識する。
身近な取組で水とトイレの安全性を守り、世界中の人々に届く支援を広げましょう!
「安全な水とトイレを世界中に」—自治体行政の関係
安全で清潔な水へのアクセスは、住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体の行政サービスとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の重要な責務です。
ゴール7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに
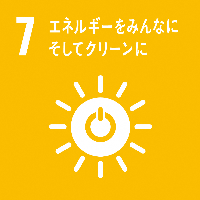
「すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する」
「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」—私達ができる身近な取組
【省エネルギーの実践】
家庭での電気やガスの使用を見直し、省エネルギーに努めることで、無駄なエネルギー消費を減らす。
【再生可能エネルギーの利用】
太陽光発電など、再生可能エネルギーの導入を検討し、環境に優しいエネルギーを利用する。
【エネルギーの節約意識を持つ】
無駄に電気をつけっぱなしにしない、エアコンの設定温度を適切に保つなど、小さな心がけでエネルギーを節約。
身近な取組を通じて、持続可能なエネルギー利用を広め、未来のためにクリーンな環境を守りましょう!
「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」—自治体行政の関係
公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住民の省エネや再エネ対策の推進を支援する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のアクセスを増やすことも自治体の大きな役割と言えます。
ゴール8 働きがいも経済成長も
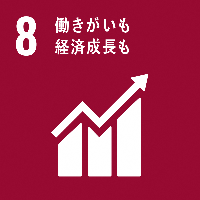
「包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する」
「働きがいも経済成長も」—私達ができる身近な取組
【地域経済の支援】
地元の商店や農産物を積極的に利用し、地域経済を活性化させる。
【働きがいのある環境づくり】
地域の労働環境の改善に関心を持ち、働きやすい職場づくりを応援する。
【地域の仕事創出に貢献】
ボランティア活動や地域イベントに参加し、地域での雇用機会を増やす取組に協力。
地域全体で支え合い、働きがいのある社会と経済成長を実現しましょう!
「働きがいも経済成長も」—自治体行政の関係
自治体は経済成長戦略の策定を通して、地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に関与することができます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して、労働者の待遇を改善することも可能な立場にあります。
ゴール9 産業と技術革新の基盤をつくろう

「強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」
「産業と技術革新の基盤をつくろう」—私達ができる身近な取組
【地元企業の支援】
地域の小規模事業者や起業家をサポートし、地元産業の発展に貢献する。
【技術の活用】
日常生活で新しい技術や便利なツールを活用し、効率的で持続可能な生活を実現。
みんなで協力して、地域の産業基盤と技術革新を支え、未来を築く社会を作りましょう!
「産業と技術革新の基盤をつくろう」—自治体行政の関係
自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の活性化戦略の中に地元企業の支援などを盛り込むことで、新たな産業やイノベーションを創出することにも貢献することができます。
ゴール10 人や国の不平等をなくそう

「各国内及び各国間の不平等を是正する」
「人や国の不平等をなくそう」—私達ができる身近な取組
【地域での平等意識の促進】
性別、年齢、障がいなどに関係なく、誰もが平等に扱われるよう心がけ、偏見をなくす。
【支援が必要な人々への手助け】
困っている人や弱い立場の人に声をかけ、助け合うことで地域の不平等を減らす。
【国際的な支援活動への参加】
募金活動や寄付を通じて、発展途上国や困窮地域の支援に貢献する。
【教育機会の平等を確保】
子どもたちに平等な教育機会を提供するため、学用品や教材を寄付する。
地域内外で、みんなが平等な機会を得られるよう支え合い、社会の不平等を減らしていきましょう!
「人や国の不平等をなくそう」—自治体行政の関係
差別や偏見の解消を推進する上でも、自治体は主導的な役割を担うことができます。少数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。
ゴール11 住み続けられるまちづくりを

「包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する」
「住み続けられるまちづくりを」—私達ができる身近な取組
【環境の保護】
地域の清掃活動に参加し、ゴミの分別やリサイクルを心がけて、クリーンで安全な街づくりを支援。
【地域の防災活動】
防災訓練に参加したり、防災グッズを準備したりして、災害に強い町づくりに貢献。
【コミュニティ活動の活性化】
地域イベントやボランティア活動に積極的に参加し、住民同士の絆を深め、助け合いの精神を育む。
【公共交通の利用促進】
自家用車の利用を減らし、公共交通機関を活用して、交通渋滞や環境への負担を減らす。
みんなで協力して、安全で快適に住み続けられる街を作りましょう!
「住み続けられるまちづくりを」—自治体行政の関係
包摂的で、安全、レジリエント(強靭さ、回復力)で持続可能なまちづくりを進めることは、首長や自治体行政職員にとって究極的な目標であり存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で、自治体行政の果たし得る役割は益々大きくなっています。
ゴール12 つくる責任つかう責任
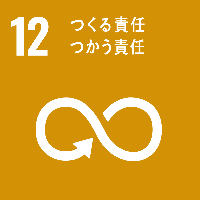
「持続可能な生産消費形態を確保する」
「つくる責任つかう責任」—私達ができる身近な取組

買い物をする際は、手前に並んでいる商品から選ぶよう心がけています。
【無駄な消費を減らす】
必要なものだけを購入し、使い捨てではなく長く使えるものを選ぶことで、資源の無駄を減らす。
【リサイクルの実践】
リサイクルや再利用を積極的に行い、廃棄物を減らして、資源の循環を促進する。
【地元産品の利用】
地元で生産された商品を選ぶことで、輸送による環境負荷を減らし、地域経済を支える。
【環境に優しい選択】
環境に配慮した商品やエネルギーを選び、持続可能な社会作りに貢献。
使う責任とつくる責任を意識して、環境に配慮した行動を広めていきましょう!
「つくる責任つかう責任」—自治体行政の関係
環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを推進するためには、町民一人ひとりの意識や行動を見直す必要があります。省エネや4R(リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル)の徹底など、町民対象の環境教育などを行うことで、自治体はこの流れを加速させることが可能です。
ゴール13 気候変動に具体的な対策を

「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」
「気候変動に具体的な対策を」—私達ができる身近な取組
【省エネルギーの実践】
家庭での電力使用を減らすために、省エネ家電を使用したり、不要な電気を消すことでエネルギー消費を抑える。
【交通手段の見直し】
自転車や公共交通機関を積極的に利用し、自動車の利用を減らして温室効果ガスの排出を減少させる。
【再生可能エネルギーの導入】
太陽光パネルや風力発電など、クリーンエネルギーを取り入れ、環境負荷を軽減する。
【地域でのグリーン活動】
植樹活動や地域の自然保護活動に参加し、森林の保護や二酸化炭素の吸収を促進する。
身近な行動が気候変動への対策に繋がります。みんなで環境を守るために一歩を踏み出しましょう!
「気候変動に具体的な対策を」—自治体行政の関係
気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求められています。
ゴール14 海の豊かさを守ろう

「持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」
「海の豊かさを守ろう」—私達ができる身近な取組

ビーチクリーン開催時の集合写真
【海岸の清掃活動】
ビーチや沿岸でゴミ拾いを行い、海洋汚染を防ぐための活動(ビーチクリーン)に参加する。
【プラスチックの使用削減】
使い捨てプラスチック製品を減らし、エコバッグや再利用可能な容器を活用する。
【環境に優しい洗剤の使用】
海洋生物に害を与えない、環境に優しい洗剤や製品を選ぶことで、海の水質保護に貢献。
【地元の漁業資源を守る】
持続可能な漁業や地域の海洋資源の保護活動に協力し、海の生態系を支える。
身近な行動が海の豊かさを守るために大きな力になります。みんなで海を守るためにできることを実践しましょう!
「海の豊かさを守ろう」—自治体行政の関係
海洋汚染の原因の8割は陸上の活動に起因していると言われています。まちの中で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講じることが重要です。
ゴール15 陸の豊かさも守ろう

「陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する」
「陸の豊かさも守ろう」—私達ができる身近な取組
【地域の自然環境を守る】
公園や森林でのゴミ拾い活動に参加し、自然環境の保護に貢献する。
【植樹活動の推進】
植樹や花を植えることで、緑豊かな環境を作り、二酸化炭素の吸収を促進。
【野生動物の保護】
地域の動植物を大切にし、自然の生態系を守るための活動に参加。
【リサイクルとエコ活動】
資源の無駄遣いを減らすために、リサイクルやエコバッグの使用を心がけ、持続可能な生活を実践。
身近な取組が、陸の豊かさを守り、未来の自然環境を守る力になります。みんなで共に環境保護に取り組みましょう!
「陸の豊かさも守ろう」—自治体行政の関係
自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有すると言えます。自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、その他関係者との連携が不可欠です。
ゴール16 平和と公正をすべての人に

「持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する」
「平和と公正をすべての人に」—私達ができる身近な取組
【地域の安全活動に参加】
地域の防犯活動や街の見守り活動に参加し、みんなが安心して暮らせる環境づくりを支援。
【差別をなくすための意識を高める】
ジェンダーや人種、障害などに対する偏見をなくし、すべての人が平等に扱われる社会を作るために積極的に行動する。
【対話と協力の促進】
地域の問題を解決するために住民同士で意見を交換し、協力し合うことで公正な社会を実現する。
【ボランティア活動への参加】
困っている人々や社会的弱者に手を差し伸べるため、ボランティア活動に参加し、支え合いの精神を広める。
平和で公正な社会は、私たち一人ひとりの意識と行動から作られます。みんなで協力して、より良い社会を作りましょう!
「平和と公正をすべての人に」—自治体行政の関係
平和で公正な社会を作る上でも、自治体は大きな責務を負っています。地域内の多くの町民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割と言えます。
ゴール17 パートナーシップで目標を達成しよう

「持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する」
「パートナーシップで目標を達成しよう」—私達ができる身近な取組
【地域コミュニティの協力】
地域のイベントや活動に参加して、みんなで協力し、目標を達成するために力を合わせる。
【異なる立場や意見を尊重】
さまざまなバックグラウンドを持つ人々と協力し、互いの意見を尊重し合いながら解決策を見つける。
【地域団体との連携】
地域のNGOやボランティア団体と協力して、共同で社会問題を解決するための活動に参加する。
パートナーシップを築き、みんなで協力することで、持続可能な社会を作り上げることができます。共に目標を達成しましょう!
「パートナーシップで目標を達成しよう」—自治体行政の関係
自治体は公的・民間セクター、町民、NGO・NPOなどの多くの関係者を結びつけ、パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で、多様な主体の協力関係を築くことは極めて重要です。








更新日:2025年11月13日