国民健康保険税について
国民健康保険税の算定方法と軽減制度について
国民健康保険税は、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金等課税分(支援分)、介護納付金課税分(40歳から65歳未満)で算定されます。
国民健康保険税の税額=(1.医療分)+(2.支援分)+(3.介護分)となります。
1.医療給付費分(医療分) 0歳から75歳未満
所得割(課税所得金額×8%)+均等割(被保険者人数×14,000円)+平等割(一世帯あたり額19,000円)
課税限度額66万円
2.後期高齢者支援金等課税分(支援分) 0歳から75歳未満
所得割(課税所得金額×4.5%)+均等割(被保険者人数×10,000円)+平等割(一世帯あたり額10,000円)
課税限度額26万円
3.介護納付金課税分(介護分) 40歳から65歳未満
所得割(課税所得金額×2.8%)+均等割(被保険者人数×14,000円)
課税限度額17万円
軽減制度
前年中の世帯(世帯主と国保被保険者)の合計基準総所得金額が次の基準以下の場合、国民健康保険税の均等割額(一人あたり額)と平等割額(一世帯あたり額)を減額する制度があります。
| 軽減割合 | 軽減対象となる世帯の基準総所得金額 |
|---|---|
|
7割軽減 |
43万円+(10万円×被保険者数[※1]ー1)以下の世帯 |
|
5割軽減 |
43万円+(10万円×被保険者数[※1]ー1)+(30万5千円×被保険者数[※2])以下の世帯 |
|
2割軽減 |
43万円+(10万円×被保険者数[※1]ー1)+(56万×被保険者数[※2])以下の世帯 |
※1 給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の合計数が2以上の場合に限ります。
※2 世帯主も被保険者数に含めます。
軽減の判定には世帯全員の所得の申告が必要です。
後期高齢者医療制度に伴う経過措置について
1.75歳になられて、国民健康保険被保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合、次の措置があります。
- 軽減判定の際、後期高齢者医療制度に移行した方の人数と所得を含めて判定します。(世帯構成と所得が変わらなければ、同じ軽減措置が受けられます)
- 後期高齢者医療制度に移った結果、国民健康保険の被保険者が一人となる場合は、平等割額(一世帯あたり額)が5年間半額になり、その後3年間は4分の1減額になります。
2.被用者保険(社会保険等)の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者で65歳以上75歳未満の者(旧被扶養者)が、国民健康保険の被保険者となる場合、次の措置があります。
- 所得割額がかかりません。
- 均等割額(一人あたり額)が半額となります。なお、旧被扶養者のみの世帯となる場合、平等割額(一世帯あたり額)が半額となります。ただし、7割、5割軽減に該当する場合は除きます。また、資格取得日から2年を経過する月までとなります。
国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について
平成20年4月から、世帯主が国保被保険者であり、65歳以上75歳未満の国保被保険者(世帯主含む)で構成される世帯(社会保険の方は除く)の国民健康保険税は、特別徴収(世帯主の年金からの天引き)されることになりました。
1.特別徴収対象者
65歳以上75歳未満の国保被保険者で構成される世帯の世帯主で、次のア、イの条件を満たす場合、国民健康保険税は世帯主の年金から特別徴収(天引き)されます。
ア.年額18万円以上の年金を受給していること
イ.国民健康保険税と、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えていないこと
例(世帯主が年額18万円以上の年金を受給している世帯)
【年金からの特別徴収となるケース】
- 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合
特別徴収(世帯主の年金から徴収されます)
(世帯主、妻ともに年齢が65歳以上75歳未満であるため) - 世帯主(国保)73歳、妻(後期)76歳の場合
特別徴収(世帯主の年金から徴収されます)
(世帯主が国保被保険者であり、65歳以上75歳未満であるため。妻は75歳以上のため除く)
【普通徴収(納付書か口座振替)となるケース】
- 世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合
普通徴収(今までどおりの納付となります)
(世帯主は65歳以上75歳未満だが、妻が65歳未満であるため) - 世帯主(後期)77歳、妻(国保)73歳の場合
普通徴収(今までどおりの納付となります)
(妻は65歳以上75歳未満だが、世帯主が75歳以上であるため)
75歳になりますと、国民健康保険被保険者から、後期高齢者医療の被保険者になります。
2.特別徴収について
年金支給月に年金から徴収されます。
仮徴収(4月、6月、8月)
当年度の国民健康保険税額が確定するまでは、前年度の国民健康保険税を基に算定された額を徴収します。
本徴収(10月、12月、2月)
確定した国民健康保険税から仮徴収された額を控除した額を3期に分けて徴収します。
特別徴収以外の方につきましては、今までどおり普通徴収(納付書または口座振替での納付)となります。
国民健康保険税の納付方法の変更について
国民健康保険税を現在、年金から天引きされている方、または新たに年金から天引きされる予定の方で、年金天引きが不都合な方は、申出書を税務課町民税係に提出することにより、年金天引きを中止し、口座振替により納付することができます。
手続きの仕方
これまで国民健康保険税を納付書で納められていた方
- 金融機関で国民健康保険税の口座振替納付の手続きをします。
- 国民健康保険税納付方法変更申出書と口座振替納付申請書の本人控と印鑑を、税務課町民税係に持参してください。
これまで国民健康保険税を口座振替で納められていた方
- 国民健康保険税納付方法変更申出書と印鑑を、税務課町民税係に持参してください。
国民健康保険税納付方法変更申出書 (Wordファイル: 33.0KB)
国民健康保険税納付方法変更申出書 (PDFファイル: 72.5KB)
国民健康保険税の減免について
国民健康保険税は、前年中の所得をもとに税額を決定しますが、失業等の原因により前年中の所得に比べて今年の所得が極端に減少し、担税能力が著しく低下した場合、保険税の減免を受けられる場合があります。
1.次の要件すべてに該当する方が、減免の対象者となります。
- 所得減少の理由が、失業、休業、廃業、疾病、負傷によるものであること
- 国保世帯の前年中の合計金額が400万円以下であること
- 当該年中の合計金額が、前年中の合計金額の2分の1以下に減少する見込みであること
2.減免の申請方法
雇用保険受給資格者証、給与明細書、離職証明書、廃業届など所得の減少理由の分かるもの及び印鑑をご持参の上、税務課町民税係にご相談ください。
申請の際には納税相談や面接を行い、総合的に判断して減免の可否を決定します。
3.減免される税額
前年中の合計金額及び当該年中の合計金額の見積額に応じ、納期未到来分の保険税の所得割額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額が減免税額となります。
| 前年中の合計金額 | 当該年中の合計金額の見積額 | 減免の割合 (所得割のみ) |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 前年中の合計金額の10分の3未満 | 10分の10 |
| 前年中の合計金額の10分の5以下 10分の3以上 | 2分の1 | |
| 300万円以下 | 前年中の合計金額の10分の3未満 | 2分の1 |
| 前年中の合計金額の10分の5以下 10分の3以上 | 4分の1 | |
| 400万円以下 | 前年中の合計金額の10分の3未満 | 4分の1 |
| 前年中の合計金額の10分の5以下 10分の3以上 | 8分の1 |
申告の状況により、減免割合の変更や取り消しになる場合があります。
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
産前産後に係る国民健康保険税軽減について(令和6年1月施行)
対象となる方・受付期間
●令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
●出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の軽減内容
●その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が軽減されます。
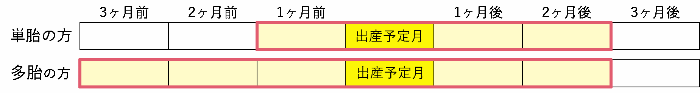
※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から軽減されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が軽減されます。
●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が軽減されます。
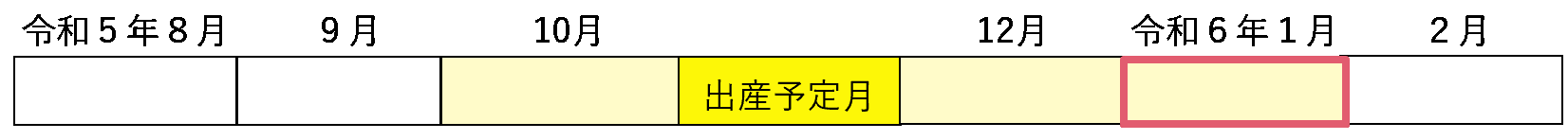
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が軽減されます。令和6年1月より前の期間については軽減の対象とはなりません。
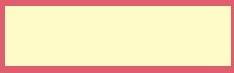 ・・・軽減対象期間
・・・軽減対象期間
●保険税が軽減された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。
届出に必要な書類
1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Excelファイル:17.6KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:85.6KB)
2.母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
3.マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)
届出先
高鍋町役場 税務課 町民税係
※届出受付は令和6年1月からとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 税務課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2011(町民税係) 0983-26-2012(収納係) 0983-26-2013(資産税係)
ファックス:0983-23-6303








更新日:2025年06月24日